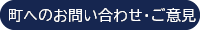公開日 2022年04月01日
国民健康保険に加入する人
上板町にお住まいの74歳以下の方は、国民健康保険以外の公的医療保険に加入している場合など※を除き、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険に加入するときは世帯単位の加入になります。
※国民健康保険に加入できない方
・被用者保険の被保険者及び被扶養者
・国民健康保険組合の被保険者
・後期高齢者医療制度に加入している方
・生活保護法の適用を受けている方
・外国人の方で在留期間か3か月以下の方、在留資格が医療を受ける目的で発給された「特定活動」の方
こんな時は届出を
国民健康保険の加入・脱退や保険証の記載内容に変更のある場合などは、事実が発生した日から14日以内に役場健康推進課へ届け出てください。
代理人による届け出の場合、委任状が必要となりますのでご注意ください。
※国保の届け出にはマイナンバーが必要です。
※国保に関する届け出、申請様式一覧 → こちらのページ
国民健康保険に加入するとき
国保資格取得届に必要事項を記入し、以下のものをお持ちのうえ役場健康推進課で手続きをしてください。
| 他の市町村から転入してきたとき |
・本人確認書類
|
| 他の健康保険をやめたとき |
・健康保険の資格喪失証明書 (様式例 健康保険資格喪失(取得)証明書[PDF:93.7KB] ) (扶養家族がいらっしゃる場合はその旨記載されたもの) |
| 生活保護を受けなくなったとき |
・保護廃止決定通知書
|
| 子どもが生まれたとき |
・母子健康手帳 ※ 出産育児一時金については、下記の<出産育児一時金の受給について>をご覧ください。 |
| 外国籍の人で上板町に住民票ができたとき |
・在留カードなど (「外交」や医療を受ける目的で発給された「特定活動」など、在留資格によっては加入できない場合があります) (住民票ができなくても3ヵ月を超えて滞在すると認められる場合は国民健康保険に加入できます) |
国民健康保険をやめるとき
国保資格喪失届に必要事項を記入し、以下のものをお持ちのうえ役場健康推進課で手続きをしてください。
| 他の市町村へ転出したとき |
・保険証
|
| 他の健康保険に加入したとき |
・国保の保険証 ・新しい健康保険証 (保険を切替えた方全員分) |
| 生活保護を受けることになったとき |
・保護開始決定通知書 ・保険証 |
| 国民健康保険の加入者が死亡したとき |
・死亡した方の保険証 ※ 葬祭費については下記の<葬祭費の受給について>をご覧ください。 |
その他の手続き
|
氏名、住所、世帯主変更等保険証の記載内容に 変更があるとき
|
・保険証 |
|
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなった とき
|
・本人確認書類 |
|
修学のため子どもが他の市町村へ居住するとき |
・在学証明書、学生証など ・修学した方の保険証 |
国民健康保険証
国民健康保険証を医療機関の窓口に提示すると、かかった医療費の一部(未就学児:2割、小学校就学後~70歳未満:3割、70歳~74歳:高齢受給者証に記載されている負担割合)を負担することで、診療を受けることができます。残りの費用は、上板町国保が負担します。医療機関にかかるときには、保険証を必ず窓口に提示してください。
<国民健康保険証の有効期限について>
国民健康保険証の有効期限は毎年3月31日です。(ただし、3月31日までに75歳になられる方は誕生日の前日が有効期限です。)
4月からの国民健康保険証は世帯主宛に世帯分をまとめて郵送します。
※国民健康保険税に滞納がある等の理由で、有効期限の短い保険証(短期保険証)を発行させていただく場合があります。
高齢受給者証
国保に加入にしている70歳~74歳の方には、国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)を交付します。
高齢受給者証は70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使用できます。
医療機関を受診するときは保険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。
<70歳~74歳の方の自己負担割合>
| 区分 | 判定基準 | 負担割合 | |
| 生年月日が 昭和19年4月1日以前 |
生年月日が 昭和19年4月2日以降 |
||
| 現役並み所得者 |
住民税の課税所得が145万円以上ある70~74歳の国保被保険者がいる世帯 ただし収入が以下のいずれかに該当する場合、申請により「一般」の区分となります。 |
3割 | 3割 |
| 一般 |
現役並み所得者、低所得Ⅰ、低所得Ⅱのいずれにもあてはまらない被保険者
|
1割 ※高齢受給者証には「2割(特例措置により1割)」と表示されます。 |
2割 |
| 低所得Ⅱ | 世帯主(擬制世帯主を含む)と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する被保険者 | ||
| 低所得Ⅰ | 世帯主(擬制世帯主を含む)と国保被保険者全員が住民税非課税世帯で、世帯員全員の所得(年金所得は控除額を80万円として計算)がいずれも0円である被保険者 | ||
※基礎控除後の所得・・・総所得金額等(前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計額。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しない)から住民税基礎控除額を控除した額
<高齢受給者証の有効期限について>
高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日です。(ただし、7月31日までに75歳になられる方は誕生日の前日が有効期限です。)
8月からの高齢受給者証は世帯主宛に世帯分をまとめて郵送します。
国民健康保険で受けられる給付
<療養費の支給について>
次のようなときは、申請により保険給付相当額が払い戻されます。
申請の際は世帯主名義の通帳など口座番号がわかるものの他に、以下のものが必要です。
| こんなとき | 必要なもの |
|
急病や旅行中の怪我など、 やむを得ず保険証を持たずに医療機関を受診したとき |
・保険証 ・診療報酬明細書 (医療機関等で発行してもらってください) ・領収書
|
| 医師が必要と認めた補装具(コルセットなど)を作ったとき |
・保険証 ・医師の証明書 ・領収書 |
| 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき |
・保険証 ・医師の同意書 ・施術明細がわかる領収書 |
| 輸血のための生血を利用したとき(親族から提供された場合を除く) |
・保険証 ・輸血を必要とする医師の証明書 ・輸血用生血受療証明書 ・領収書 |
|
海外渡航中に医療機関を受診したとき(治療目的の渡航を除く) ※詳しくはお問合せください |
・保険証 ・パスポート ・診療内容明細書 (日本語の翻訳を必ず添付してください) ・領収明細書 (日本語の翻訳を必ず添付してください) ・調査にかかわる同意書 |
※申請から支給まで2~3か月お時間をいただく場合がございますのでご了承ください。
<高額療養費の支給について>
・高額療養費制度とは
同じ月内の医療費の負担が高額となり一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分の金額を後から払い戻す制度です。
※あらかじめ医療機関窓口での負担を減らしたい場合は、下記の<限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行について>をご覧ください。
・高額療養費の計算のしかた
【70歳未満の方の場合】
1.暦月(月初から月末まで)ごとの受診について計算します。
2.受診された人ごとに計算します。
3.一つの医療機関ごとに計算します。
4.同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々に計算します。
5.保険適用分として負担した額(一部負担金)のみで計算します。差額ベッド代や食事代は対象外です。
6.一つの世帯で1~5により計算した一部負担金のうち、21,000円以上のものが二つ以上ある場合はそれを合算します。
【70歳~74歳までの方の場合】
1.外来は個人単位でまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
2.自己負担金額が少額であっても合算することができます。
自己負担限度額は下の表のとおり、年齢や世帯の所得、住民税の課税状況などで判定します。
当月を含む過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が下がります。
【70歳未満の方の自己負担限度額】
| 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 (3回目まで) | 4回目以降 | ||
| ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
医療費が842,000円 252,600円 + を超えた場合は、 その超えた分の1% |
140,100円 | ||
| イ |
基礎控除後の所得 |
医療費が558,000円 167,400円 + を超えた場合は、 その超えた分の1% |
93,000円 | ||
| ウ | 基礎控除後の所得 210万円超 600万円以下 |
医療費が267,000円 80,100円 + を超えた場合は、 その超えた分の1% |
44,400円 | ||
| エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | ||
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | ||
※基礎控除後の所得・・・総所得金額等(前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計額。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しない)から住民税基礎控除額を控除した額
【70~74歳の方の自己負担限度額】
| 区分 | 負担割合※ | 自己負担限度額 | |||
| 外来(個人単位) | 入院 | 世帯単位 | |||
| 現役並み所得者 | Ⅲ | 3割 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(140,100円) |
||
| Ⅱ | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(93,000円) | ||||
| Ⅰ | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(44,400円) | ||||
| 一般 | 1割 または 2割 |
14,000円 (年間144,000円) |
57,600円(44,400円) | ||
| 低所得者 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
| Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | |||
※( )内の金額は多数該当(直近1年の間に3か月以上高額療養費の支給を受け4か月目以降の支給に該当)の場合。
※負担割合については「70歳~74歳の方の自己負担割合」をご覧ください。
現役並み所得Ⅲ・・・課税所得が690万円以上の70歳~74歳の国保被保険者及び同一世帯の70歳~74歳の被保険者
現役並み所得Ⅱ・・・課税所得が380万円以上690万円未満の70~74歳の国保被保険者及び同一世帯の70~74歳の被保険者
現役並み所得Ⅰ・・・課税所得が145万円以上380万円未満の70~74歳の国保被保険者及び同一世帯の70~74歳の被保険者
低所得者Ⅱ ・・・世帯主(擬制世帯主を含む)と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する被保険者
低所得者Ⅰ ・・・低所得者Ⅱの条件を満たし、かつ世帯員の各所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円である世帯に属する被保険者
・支給申請の流れ
1.受診月の2~3か月後に高額療養費支給のお知らせが届きます。
2.以下のものを持参のうえ役場健康推進課で申請します。
<お持ちいただくもの>
・医療機関等の領収書
・通帳など、世帯主の口座番号がわかるもの
・本人確認書類
・マイナンバーカードなど
3.世帯主名義の通帳に高額療養費が振り込まれます。
<限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行について>
医療費が高額となる場合は、あらかじめ限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け医療機関窓口に提示することで、窓口での支払は自己負担限度額までとなります。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用とならない費用は対象外です。
※70歳以上で一般世帯に属する方は、高齢受給者証を提示することで自己負担限度額までの適用となるため、認定証の発行はございません。
※認定証の交付にあたっては、原則、国民健康保険税に滞納がないことが条件となります。
・申請方法
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書に必要事項を記入し、国民健康保険証、印かんをお持ちのうえ、役場健康推進課の窓口にてご申請ください。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書[PDF:78.7KB]
・認定証の発行期日と有効期限
発行期日・・・申請月の1日まで遡って認定されます
(申請月の前月に遡っての認定はできませんので、後日高額療養費の支給を受けてください。)
有効期限・・・毎年7月末日
(8月以降も認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。)
<入院時食事療養費>
入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に一定の額(標準負担額)を加入者が支払い、残りを国保が負担します。
・入院時の食事にかかる標準負担額
| 一般の被保険者(下記以外の人) | 1食 460円※1 | |
|
住民税非課税世帯及び 70~74歳で低所得者Ⅱの人※2 |
90日までの入院 | 1食 210円 |
|
過去12か月の入院日数が 90日を超える入院 |
1食 160円 | |
| 70~74歳で低所得者Ⅰの人 ※2 | 1食 100円 | |
※1 指定難病の方等は260円です。
※2 住民税非課税世帯及び70~74歳で低所得Ⅰ,Ⅱに該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、税務課窓口で申請してください。
<高額介護合算療養費>
医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったときの負担を軽減するため、医療保険制度で高額療養費の対象になった世帯に介護保険の受給者がいる場合に、両者の自己負担額を合算できるようになります。
自己負担額は年額で定められ、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されることになります。高額介護合算療養費の支給が見込まれる方については、役場健康推進課より支給申請書を送付させていただきます。
・合算した場合の自己負担限度額(年額<8月~翌7月>)
70歳未満
| 所得要件 | 限度額 | |
| ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
2,120,000円 |
| イ |
基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 |
1,410,000円 |
| ウ |
基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 |
670,000円 |
| エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
600,000円 |
| オ |
住民税非課税世帯 |
340,000円 |
70~74歳
| 所得区分 | 限度額 | ||||
| 現役並み所得者 | Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 2,120,000円 | ||
| Ⅱ |
課税所得 380万円~690万円未満 |
1,410,000円 | |||
| Ⅰ | 課税所得 145万円~380万円未満 | 670,000円 | |||
| 一般(課税所得145万円未満等) | 560,000円 | ||||
| 低所得者 | Ⅱ | 310,000円 | |||
| Ⅰ | 190,000円 | ||||
<特定疾病療受療証>
国民健康保険に加入している方で以下の対象疾病に該当する方は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を発行することができます。特定疾病療養受療証を医療機関に提示すると、自己負担限度額で対象疾病の治療を受けることができます。
・対象疾病
(1)人工透析を行う必要のある慢性腎不全
(2)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
・自己負担限度額と有効期限
(1)の対象疾病の1か月の自己負担限度額と有効期限については以下のとおりです。
| 上位所得者 | 上位所得者以外 | 有効期限 | |
| 70歳未満 | 20,000円/月 | 10,000円/月 | 毎年7月31日 |
| 70歳以上 | 10,000円 / 月 | なし | |
※上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯に属する方
(2)(3)の対象疾病について、1か月の自己負担限度額は10,000円で有効期限はありません。
・申請方法
国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書の医師の意見欄を病院で記入してもらったうえで、役場健康推進課課の窓口にてご申請ください
・必要なもの
・国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(医師の意見欄に記入があるもの)
・国民健康保険被保険者証
出産育児一時金の受給について
国民健康保険に加入している方が出産されたとき、申請により出産育児一時金42万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は40万4千円。ただし、平成26年12月31日以前の出産は39万円)が支給されます。
妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産の場合でも支給が受けられます。
※注意※
・出産日時点で国民健康保険に加入していても、他の社会保険の被保険者として1年以上加入しており、社会保険を喪失してから6か月以内の出産の場合は、社会保険から出産育児一時金が支給されます。
・出産育児一時金の給付を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となりますので、お早めに手続きにお越しください。
◎産科医療補償制度
あらかじめ分娩機関が保険に加入しておくことで、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する経済的補償を行う制度。対象となるのは、この制度に加入し ている分娩機関で出産し、妊娠週数22週以上の場合です。詳しくは、財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
◎直接支払制度について
直接支払制度とは出産育児一時金を直接出産費用に充てることができるよう、保険者から医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度です。
この制度を利用すると、窓口での費用負担を出産育児一時金の額の分、軽減することができます。なお、同制度を利用できない医療機関がありますので、詳しくは医療機関にお問合せください。
直接支払制度を利用しなかった場合は、役場健康推進課の窓口で申請することにより出産育児一時金が支給されます。
また、直接支払制度を利用し、かつ出産育児一時金が出産費用を上回った場合は、その差額が支給されます。支給は原則、世帯主名義の口座にお振込みさせていただきます。
・申請方法
出産育児一時金受給申請書と国民健康保険証、世帯主名義の通帳等口座番号がわかるものをお持ちのうえ、役場健康推進課の窓口にてご申請ください。
葬祭費の受給について
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬祭を行った方に対して2万円が支給されます。
申請は役場健康推進課の窓口で行えます。
・申請方法
葬祭費受給申請書に必要事項を記入し、以下のものをお持ちのうえ役場税務課の窓口へご申請ください。
・必要なもの
・喪主名義の通帳など口座番号がわかるもの
・死亡した方の保険証(返却済みの場合は不要)
給付の制限
次のような場合は国民健康保険の給付が受けられなかったり制限されたりします。
<給付が受けられないもの>
・正常な妊娠や出産
・歯列矯正や美容整形
・他の保険が適用される場合(労災保険など)
<給付が制限されるもの>
・酒酔いやけんかが原因のけがや病気
・犯罪や故意によるけがや病気
交通事故にあったとき
交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)によってけがをした場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合、かかった医療費は国民健康保険が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
交通事故にあったら、すぐに警察に届け事故証明書を受け取り、必ず国民健康保険の窓口へ第三者行為による傷病届を提出してください。
<届け出に必要なもの>
・第三者行為による傷病届の様式等(外部サイトへ移動します)
・国民健康保険証
・マイナンバーカード等個人番号がわかるもの
<示談は慎重に>
加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され国民健康保険から加害者に請求できなくなる場合があります。またすでに加害者から治療費を受け取っているときは、国民健康保険を使うことはできません。
示談の前に必ず国民健康保険に届け出をするようにしましょう。
特定健康診査を受診しましょう
<特定健康診査とは>
生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を早期に発見するため、平成20年度に始まった健康診査のことです。
腹囲や身長、体重、血圧、血液などを検査します。基準値以上の場合(腹囲なら男性85センチ、女性90センチ以上)、食生活や運動習慣について特定保健指導を受ける対象になります。
この機会にぜひ健診を受診しましょう。
<特定健康診査の対象者>
4月1日現在に国民健康保険に加入している40歳~74歳の方
※4月1日~9月30日までに75歳になる方は、後期高齢者医療保険の健康診査対象者となりますので、国民健康保険から受診券は発行されません。
※4月2日以降に国民健康保険に加入した方で特定健康診査の受診を希望される場合は、役場健康推進課へお問い合わせください。
対象者には7月上旬に受診券を送付します。
<特定健康診査の受診期間>
毎年1月31日まで
※ただし、10月1日~翌年3月31日までに75歳になる方は、75歳の誕生日の前日か1月31日のいずれか早い日まで
<特定健康診査の受け方>
受診回数は1回です。いずれかの方法で受診してください。
・医療機関で受診・・・特定健康診査受診券に同封されている県内実施医療機関一覧表に記載されている医療機関で受診できます。
・上板町保健相談センターで受診(集団検診)
<マイナポータルで特定健診情報の閲覧が可能になります>
マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータルの利用者登録をした方については、健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。
詳しくは、マイナポータルのわたしの情報ページ(外部サイト)をご覧ください
ジェネリック医薬品を活用しましょう
医療機関で医師から処方される薬には、新薬(先発医薬品)と呼ばれるものと、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
ジェネリック医薬品の利用を促進して、医療費を適正化するための取り組みが進められています。そこで、ジェネリック医薬品の意義やその使用法について理解をしておきましょう。
<ジェネリック医薬品とは>
・新薬と同じ成分、同じ効き目で安い薬です
ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れてから作られた薬です。厚生労働省により新薬と効き目が同等と認められたものが製造されています。
・開発期間が短くて済む分、価格が安いです
新薬は開発に長い時間と多くの費用がかかりますが、ジェネリック医薬品は開発期間が短くて済むので、価格が安くなります。
※窓口でお支払いいただく患者負担金は、お薬の費用のほか、調剤料などが加わります。
・ずっと使われている薬なので、安心です
ジェネリック医薬品のもととなる新薬は特許が切れるまで、ずっと使われた薬です。ですから、安全性や効き目は折り紙つきです。
<ジェネリック医薬品は医療費削減に役立ちます>
ジェネリック医薬品の価格は新薬の3割以上、中には5割以上安くなる場合もあります。ジェネリック医薬品に変えることで、薬代は安くなります。経済的な負担が減るので、安心して医療を受けることができます。また、家計だけでなく、上板町の医療費の軽減にも大きく貢献し、医療制度を守るために役立ちます。
<ジェネリック医薬品を希望するときは>
ジェネリック医薬品を希望するときは、まず医師に相談をして、その選択や使用法については薬剤師と相談してみましょう。すべての医薬品にジェネリック医薬品が存在するわけではなく、治療内容によってはジェネリック医薬品が適さない場合もあります。
もし、自分から言い出しにくい場合には、ジェネリック医薬品の処方を希望するカードを提示することで、意思表示をすることができます。
※ジェネリック医薬品希望カードは、保険証を送付する際に同封されている「国保のしおり」に添付されています。国保のしおりは役場税務課にも用意しておりますので、必要な場合はお問い合わせください。
<不安なときは医師や薬剤師に相談しましょう>
ジェネリック医薬品の使用に不安がある場合は、医師や薬剤師に相談してみましょう。また、実際に服用した場合でも、効き始めるまでや、効果が続く時間に変化がないか、効き目は同じかなどに注意して、薬の変更前と異なるようでしたら、すぐに医師や薬剤師に相談しましょう。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード