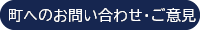公開日 2025年04月01日
1.国民健康保険税について
国民健康保険税(以下、国保税)は国保に加入するみなさまが病気やけがをしたときの医療費をまかなうための大切な財源です。この財源が不足すれば国保から十分な給付を受けられなくなるおそれもあります。
国保税は期日内にきちんと納め、国保の健全運営にご協力お願いします。
2.納税義務者について
国民健康保険税は世帯主に対して課税されます。
世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険等に加入している場合)でも、世帯に国保の被保険者がいるときは、世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主)。
3.国保税の計算方法
保険税の課税額は世帯主(被保険者でない世帯主を除く)及びその世帯に属する国保被保険者について算定した所得割額、被保険者均等割額並びに世帯平等割額の合算額です。
介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)がいる世帯については、国保税に介護保険料が含まれます。
令和7年度の税率
国民健康保険法の改正により、平成30年度から徳島県が財政運営の責任主体となりました。「徳島県国民健康保険運営方針」において、「資産割」廃止による3方式移行に伴い、資産割を段階的に減額し、令和5年度から資産割の賦課を廃止しています。資産割の廃止に伴う保険税減少分は、所得割、均等割、平等割に配分いたします。国民健康保険加入者の皆さまには、健全な国保運営のためご理解とご協力を賜りますようお願いします。
| 国民健康保険税 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
| 所得割額(課税対象額※1に次の比率を乗じた額) | 9.5% | 2.8% | 2.0% |
| 資産割額 | 0% | 0% | 0% |
| 均等割額(被保険者一人あたり) | 25,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
| 平等割額(1世帯あたり) | 20,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 課税限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
※1 課税対象額 国保被保険者の前年中の総所得金額から43万円を控除した額
4.国保税は資格が発生した月から課税されます。
国保加入の届け出が遅れてしまった場合でも、届け出をした月ではなく国保の資格が発生した月(他の健康保険の喪失月、上板町に転入した月など)までさかのぼって国保税が課税されることになります。
5.国保税の納付方法及び納期限について
国保税の納税通知書は毎年7月上旬にお送りします。
通常、1年分(4月から翌年3月までの分)を8回に分けて納めていただきます(普通徴収)。また、年金からの特別徴収の場合は偶数月の年金受給日において年金から天引きさせていただきます。
納期限は各納期の末日(12月は25日)ですが、金融機関の休日にあたる場合はその翌日になります。
| 徴収方法 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 普通徴収 |
ー |
ー | ー | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ー |
|
特別徴収(年金からの天引き) |
〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー |
※年度の途中で加入された方は、届出の月により納付回数が異なります。
6.国保税の軽減制度
世帯所得による軽減
所得や固定資産がない場合でも、均等割と平等割は課税されます。
ただし、所得が一定の基準以下の世帯については均等割額と平等割額が軽減されます。
| 判定所得 | 判定区分 | 軽減割合 |
|
世帯主とその世帯の国保被保険者 及び特定同一世帯所属者の 前年中の総所得金額等の合計額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 7割 |
| 43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 5割 | |
| 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下の世帯 | 2割 |
※軽減判定日(軽減できるかを判定する日)は毎年4月1日、またはその世帯が4月1日以降で最初に国保資格を取得した日となります。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国保から脱退した方のうち、同じ世帯に国保被保険者がいる方をいいます。
※農業所得や事業所得における専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった方は専従者給与がなかったものとして判定します。
※65歳以上で公的年金を受給されている方については、公的年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
※譲渡所得については特別控除前の金額で判定します。
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減
1 特定世帯及び特定継続世帯に対する減額
国保から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保加入者が1人になる世帯は、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が5年間半額になり(特定世帯)、その後3年間4分の3になります(特定継続世帯)。
2 旧被扶養者に対する減免
被用者保険(社会保険や共済組合など)に加入していた方が後期高齢者医療制度の加入者になったため、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を旧被扶養者といいます。
この場合、旧被扶養者の方の所得割額と資産割額は課税されず、均等割額は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額となります。また、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額になります(世帯所得により7割、5割軽減に該当している場合は除く)。
※旧被扶養者減免を受けるためには役場税務課に申請が必要ですので、詳しい申請方法等はお問い合わせください。
解雇などによる失業者に対する軽減
平成22年4月から、勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、国保税を次のとおり軽減しています。
【対象者】
平成21年3月31日以降に離職し、離職日時点65歳未満で、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由が以下の番号となっている方。
・特定受給資格者 ⇒ 離職理由番号 11、12、21、22、31、32
・特定理由離職者 ⇒ 離職理由番号 23、33、34
※雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証の場合は対象となりません。
【軽減内容】
対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を算定します。
※平成22年度から、高額療養費などの所得区分判定も軽減後の所得で判定します。
【対象期間】
離職日の翌日からその翌年度末までの期間
【申請方法】
国民健康保険証、雇用保険受給資格者証、印鑑を持参のうえ役場税務課にてご申請ください。
未就学児にかかる均等割額の軽減
令和4年度から未就学児にかかる均等割額が軽減されます。
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。
【軽減の対象者】
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
【軽減内容】
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割をさらに5割減額することとなります。
例えば、均等割額の7割軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となします)
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は、不要です。